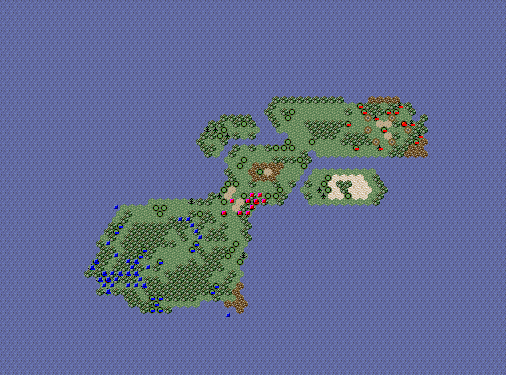
ここでは、アドバンスド大戦略98のマップをプレーしてみた戦記を紹介する。キャンペーンモードでは、既に一年前にクリアしているし、もし再開するとなると凄まじい時間が必要になるので、シナリオモードのマップを改造してプレーすることにした。以下には、プレーの内容がズラズラと書かれているが、このゲームを持っていない人でも楽しめるように、できるだけ本物の戦場に見立てて書いたつもりである。
アイランドキャンペーン(改)
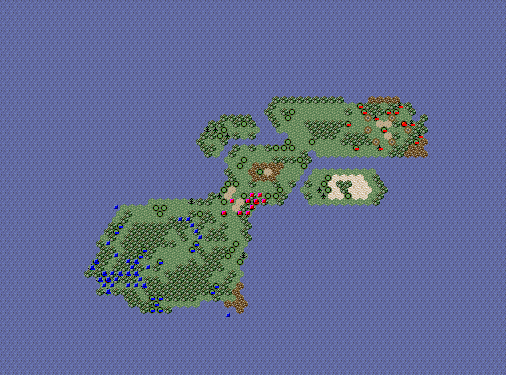
このマップは昔から、多くの大戦略ER(ダイセンリャカー)に愛されてきた古戦場であり、ほぼ全ての大戦略シリーズに収録されているマップだ。大まかに説明すると大きく2つの島からなっており、下側(南東)の島がプレイヤー、上側(北東)側がCPUの領土と言ったところだ。上側の島はさらに4つに分かれており、左と下側に小さな島が橋で繋がっている。マップ中央の島は全ての島と接続されており、激戦が予想される。ただ、若干面白さを増すためにマップのど真ん中(中央の赤いブツブツのあたり)に敵の首都(前線基地)を追加した。これを攻略すると北東の首都に遷都するしくみだ。また、純粋な戦術戦を楽しむために、工作車、爆撃機等は生産禁止である。プレイヤーはソ連の生産型で、ペトロパブロフスク級巡洋艦、アルハンゲリスク級戦艦を初期配置で持っている。対するCPUはイタリア生産型で初期配置なし。開戦日は1945年1月1日、索敵、天候ルール共になし、軍事予算は共に最高額である。
ソ連
セガ大戦略シリーズはドイツ中心主義なので、ソ連は敵国として登場する機会が多かったが、その恐るべき強さは実際に対戦してみないと分からないだろう。史実では、ソ連は常に独軍に対して数で圧倒した戦いを展開していた。ゲームでもコストパフォーマンスの高い兵器群が中心であり、敵としては侮りがたい。しかし、プレイヤーが操作する生産型としては、やや力不足であろう。数で圧倒したくても資金がいるし、部隊数の限界は他の生産型と同じ64部隊である。さて、ここで各種兵器を見ていこう。まず空軍である。当時、陸軍直協空軍と言われただけあって、対地支援能力はそこそこ高いが、戦闘機同士の戦闘となると劣性である。独軍、英米軍が相手では、一方的にたたき落とされるのがオチである。また、全体的に航続力が短いのも難点となる。陸軍については強力な戦車部隊があり、T-34は使いやすいし、JS戦車などは最強クラスである。しかし、他の支援兵器はお粗末で、トラックベースだったりする。ただ、自走ロケットトラック(BM-13等)は使えるので、大量生産したいものだ。また、時の国家元首であったスターリンの砲兵至上主義を反映してか、砲兵部隊が強力である。もっとも、プレーヤーが使うには、あまりにも機動力が足りなくて使いづらいだろうが...。海軍は、そこそこといったところ。とりあえず、戦艦も潜水艦もある。どちらにしろ、特殊な状況でない限り活躍することはないであろう。
大戦略シリーズにおいての伊軍は、中国軍と並んで弱い生産型の代名詞となっている。しかし、兵器には独特なものも多く、マニアには見逃せない。空軍の戦闘機は意外に強い。武装は弱めだが空戦能力が高い機体が多いのだ。戦略爆撃の提唱者であるドゥーエの思想を組む空軍ではあるが、爆撃機には特に注目すべき機体はない。陸軍はかなり弱く、自走砲がなんとか使える程度。海軍はバランスがよく、全般的に防御力は低いが足が速く、高性能な艦が多い。戦場さえ許せば活躍の場は多いだろう。商船の船体を利用した空母アキラ級(2番艦スパルビエロ)の存在が光っている。
ここで、我がソ連空軍の主力となる航空機を紹介しておこう。選択肢は極めて少ない。実際に大戦中に活躍したYak-3(戦闘機)、Yak-9(戦闘爆撃機)ぐらいしかない。空戦能力では前者が若干リードしているが、後者は対地攻撃用の爆弾、ロケット弾が搭載可能なうえに航続力も若干長い。そのため、総合能力で勝るYak-9のみの生産とする。伊空軍の戦闘機は侮りがたい。合流をうまく使って全滅しないように慎重に使い、経験値を高めるつもりだ。Il-2は対地攻撃以外に使い道がなく、不便なので今回は不参加だ。
地上部隊は戦車がT-34(1943年型)である。兵器は純ソ連製に限る。シャーマン戦車などは邪道である。歩兵と補給部隊は選択の余地なく動員兵、補給馬車を使用する。自走砲はソ連陸軍お得意の「スターリンのオルガン」ことBM-13を使用する。あとは、輸送トラックと85mm高射砲を生産する。
艦艇に関しては、対潜水艦用にグネフヌイ級の駆逐艦を2隻建造し、ペトロパブロフスク、アルハンゲリスクとそれぞれ戦隊を組み、前者の東進部隊を第一戦隊、後者の北進部隊を第二戦隊と名付けて使用する。
戦闘開始早々、ペトロパブロフスクは東から陸沿いに進路をとり、北上する。同じくアルハンゲリスクは軍港から北上を開始し、西進する。共に進撃する地上部隊の支援のために先行するのだ。すぐに戦闘機を生産し、直援に向かわせる必要があるだろう。歩兵部隊は扇状に展開し、街や空港、港などの軍事施設を占領する。先発の戦車部隊は中央部を急進撃し、早くも3日目には伊地上部隊と交戦状態に突入した。それに先立ち、YaK-9で編成された我が地上襲撃部隊は伊地上部隊にロケット弾攻撃を加えた。5日目にはペトロパブロフスクが艦砲射撃を開始し、伊地上部隊に大打撃を与えた。同じく5日には、敵前線基地から後方の首都に遷都した。しかし、この周辺には敵の残存部隊がひしめいており、その中にはRe2005戦闘爆撃機の姿も見える。Yak-9ではとても太刀打ちできない程の相手である。急いで高射砲を生産してZIS-5トラックで前線に輸送するも間に合わず、次々に我が航空部隊が食われる始末。また、T-34もカタログデータは高いものの、発射速度が遅いため敵に先に攻撃されてしまう。動員兵では街ひとつの占領にも3〜4日かかるので、なかなか進撃はおぼつかない。BM-13だけが強力な攻撃力で敵を粉砕してくれるが、射程は短く、防御力も皆無である。ここにきてソ連軍は、なかなかのプレーヤー泣かせな生産型であることを実感した。
伊軍は、遷都早々にカピターニ・ロマーニ級巡洋艦、チクローネ級駆逐艦を起工した。しかし、なぜか完成を待たずに出撃している。これは我が水上打撃部隊にとってはいいカモである。他にも陸空、双方とも部隊の再編を始めている。「あっ」と言う間にM15/42中戦車を中核とする戦車部隊を編成してしまった。しかし、これらの地上部隊はT-34を中核とする我軍の親衛戦車軍が一瞬にして撃滅してくれることだろう。問題は敵のRe2005、G55等の5シリーズ戦闘機だ。航続力は長く、戦闘力も強力なので我航空軍では手に負えない。前線の空港を押さえて少しでも行動範囲を押さえるしかあるまい。
伊軍は、散発的ではあるが絶え間なく部隊を送り込んでくる。我が軍はこれを逐次迎撃すると共に、増えすぎた部隊を再編成して、ふたつに分けることにした。一方は島の北側を進む第一親衛戦車軍。もう一方を南の島づたいに進撃させる第二親衛戦車軍とした。航空部隊も同じく編成替えを行った。第一親衛戦車軍を援護する第一航空軍。同じく、第二親衛戦車軍の援護に第二航空軍を編成した。艦艇部隊は、前者に第二戦隊、後者に第一戦隊をそれぞれ支援に向かわせた。これら、二方面の陸海空部隊を統合して、北部部隊を北部戦線正面軍、南部部隊を南部戦線正面軍とした。
さて、中央部を制圧したはいいものの、歩兵が追いつかずに占領が出来ないままでの進撃となった。しかも、時を同じくして伊軍の本格的な攻勢も開始され、補給の不十分なまま、我が軍は各地で苦戦を強いられる羽目になってしまった。伊空軍は戦闘機部隊を編成しては前線を越え、我が航空部隊を頻繁に攻撃してくる。既に高射砲部隊の一部が前線に到着しており、かなりの被害を与えることに成功している。第一戦隊は、我が軍初の艦隊戦を経験した。西進してきた伊駆逐艦2隻を遠距離からの艦砲射撃と魚雷で撃沈したのだ。
歩兵部隊の到着と拠点の占領、部隊の再編成、補給が整い、新たに攻勢作戦を発起できたのは、1/22になってからのことであった。
それ以後は、一歩一歩進んでいくという戦いとなり、矢継ぎ早に投入される敵の新鋭戦力をいかに少ない損害で撃破できるかに戦闘の焦点が移っていった。敵飛行場の周辺に高射砲部隊を配置し出すと、敵航空戦力の配備と同時に損害を与えられるようになったので、かなり楽になった。日に日に包囲網は狭まっていき、敵の配備が一カ所に集中し出すと陸空からのロケット攻撃が功を奏し、一挙に敵軍壊滅に至った。
このマップは、10年以上前から幾度となくあらゆる大戦略シリーズで体験しているので、自ずと攻略法は同じとなる。まあ、どうやっても負けることのないマップだとは思う。問題は今回、自軍に使用した生産型である。ソ連軍がこれほど使い辛い生産型だとは思っても見なかった。また、同時に対戦した伊軍の長所、短所も浮き彫りにしている。こういった意味で、いい経験となった。いろんな生産型で試してみて、その良いところ、そして悪いところを把握するには非常に良いマップなのだ。とりあえず、今回はここまで。